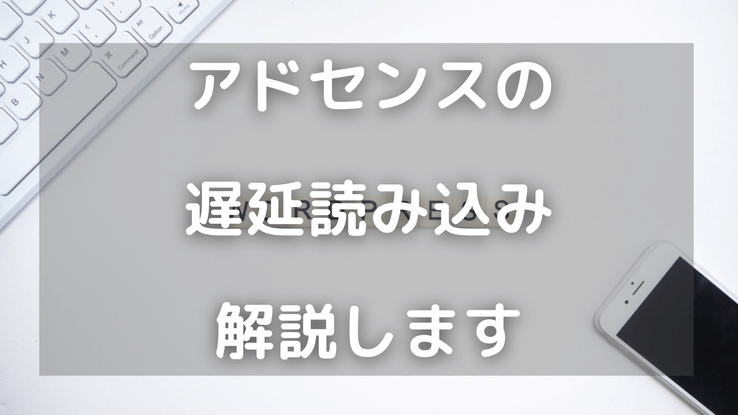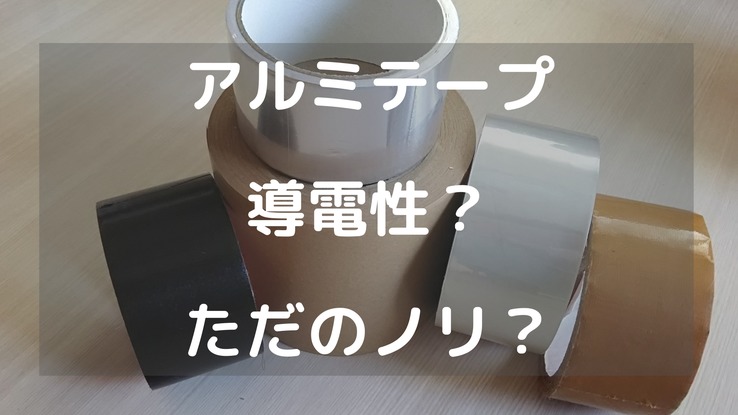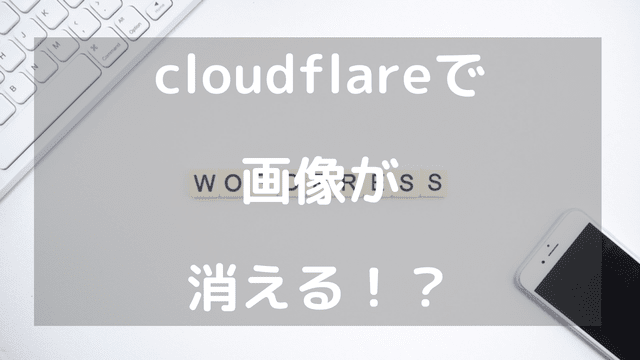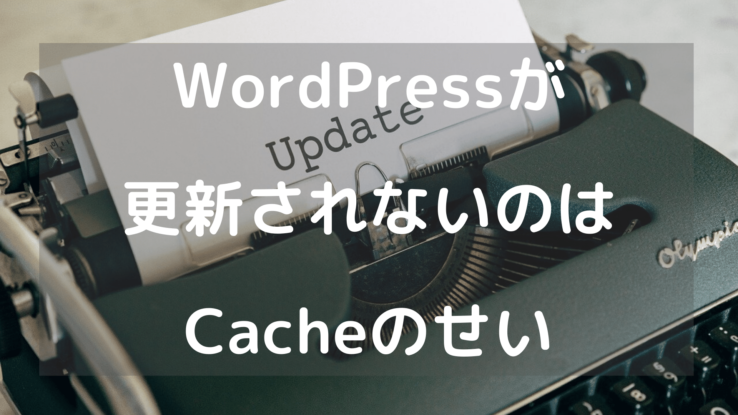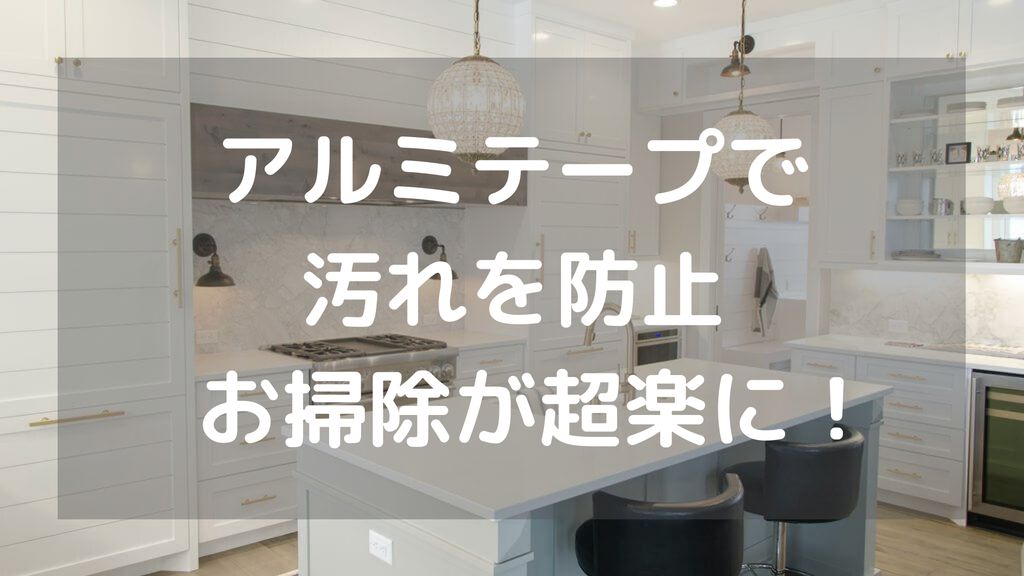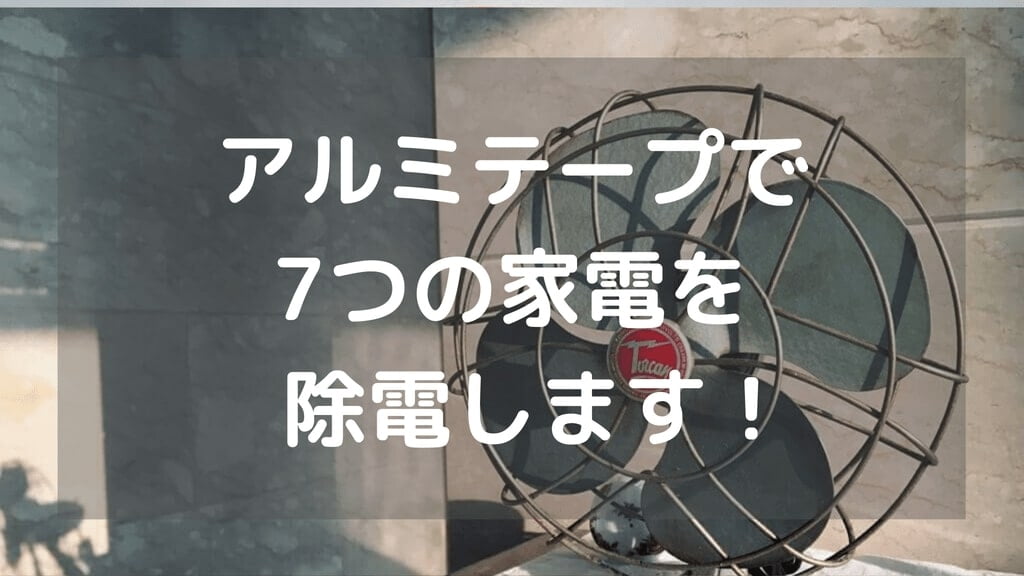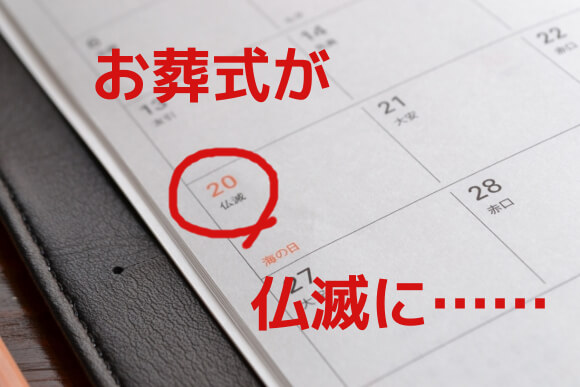親族が亡くなり、葬儀の日程を考えていくと、どうやらお葬式は仏滅になりそう……
これ実際にわたしが父を亡くした時に直面したパターンなんです。
葬儀の日時など決める時にわかったんですけど、
詳しそうな人に電話してみたりしましたね〜、かなり悩みました。
お葬式を仏滅にするとか…
めちゃめちゃ縁起悪そうじゃないですか?
仏滅の次の日が大安ですから伸ばせないかと相談しましたが、
結局はお寺さんや親族の都合もあって選べなかったんです。
でも後になってよくよく調べてみて判明したんですけど、、、
ちょっとガックリきましたけどね、
あの時なやみまくった私の立場は…と(苦笑
ここでは私が六曜とお葬式について調べてきたこと、
- 仏滅や大安、「六曜」の由来
- 仏教・神道・風水などとの関係
- 仏滅が避けられる本当の理由
についてお伝えしていきますね。
六曜について
| 六曜 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| 大安 | たいあん だいあん | 大いに安し |
| 赤口 | しゃっこう せきぐち | 正午前後のみ吉 それ以外は凶 |
| 先負 | せんしょう さきがち | 先んずれば即ち勝つ 午後2~6時は凶 |
| 友引 | ともびき | 凶事に友を引く |
| 先負 | せんぶ さきまけ | 先んずれば即ち負ける 午前は凶・午後は吉 |
| 仏滅 | ぶつめつ | 仏も滅する大凶日 |
カレンダーにも載ってる「六曜」と呼ばれるものです。
家を新築するときの棟上げ式や結婚式、
今回のテーマであるお葬式の日取りなど、
この六曜を意識して決定されるのが夜の習わし的な感じですよね。
ですが、「いつ」「だれが」言い出したのか?
そしてそれぞれの曜日に意味がつけられていますが、その根拠は何なのか?
実は、なにもかもが不明なんです。
一節には中国の三国時代、諸葛孔明が考案したという説もあるのですが、
これも実際のところは後世のひとが言い出した想像でしかありません。
それが誰かも不明です。
なのにどうしてこんなに広まって、信じる人が多いのか?
それについては最後の「おまけ」コーナーでお話しようと思います。
つぎにそのお葬式をあげる仏教や神道などの宗教との関係について見て行きましょう。
宗教と六曜
六曜のなかでも最も不吉な「仏滅」
その「仏」という漢字から仏教の教えだと思っている方も多いですね。
わたしもその一人でしたし(苦笑
ですがそれは大間違いでした。
これ知った時はほんとうにビックリしてしまったんですが…
否定していたというより、「禁じていた」のです。
引用:
わが徒は、アタルヴァ・ヴェーダの呪法と夢占いと相の占いと星占いとを行なってはならない。鳥獣の声を占ったり、懐妊術や医術を行なったりしてはならぬ。
六曜はその日その日の吉凶を占う類のものですから、当然アウト。
これ知った時に思い出したんですけど、わたしが父の葬儀で悩んでた時、
お寺さんが「そんなに気にせんでええよ〜」と言ってくれていたんです。
もうちょっとちゃんと説明してくれてたら、とも思いますが
「お葬式が仏滅だなんて絶対ダメだ!」
と譲らない方もいますよね。
きっとそういう人もいるとわかった上でやんわりと言ってくれてたんだな〜、と。
他の宗教とも関係ない
はじめにお話したとおり、
六曜の出処(でどころ)も根拠(こんきょ)も不明です。
ですから仏教はもとより神道とも関係ありませんし、キリスト教とも無縁です。
あと、「風水」が由来かとも思ったのですが、それもどうやら無関係。
なぜかというと、六曜は単にひと月を5で割って割り振ったものであり、
星や月の運行とも関係ないのです。
風水学や四柱推命などは天体との相関関係が中心です。
六曜算出サイト
[sc_Linkcard url="http://keisan.casio.jp/has10/SpecExec.cgi?path=01200000.%82%B1%82%E6%82%DD%82%CC%8Cv%8EZ%2F03000000.%8B%8C%97%EF%81E%97%EF%92%8D%2F10000300.%98Z%97j%8Cv%8EZ%2Fdefault.xml"]
こんな風に機械的に決められる曜日に運勢が左右されるとは、ちょっと考えられませんよね。
ただし、信じている人は本当に信じきっていますから、
お葬式を仏滅に行ったあと、病気やケガなどしようものなら・・・
「だからアカンて言うたやん!」
なんてドヤ顔で難癖つけられかねません。
この点だけは今でも六曜を気にしないといけない理由じゃないかなと思われます^^;
では、いったい誰がどんな理由で六曜をここまで広め信じさせたのか?
こちらも一節にすぎませんので「おまけ」として紹介しておこうと思います。
おまけ|六曜が広められた理由
これは六曜を世の中に広め、強烈に信じさせた理由ではないかといわれている一節です。
わたしたち一般人は日曜日はお休みだったり、定期的に休日を取れますよね。
でも、葬儀など予期できない行事に携わる人たち。
とくにお葬式などは亡くなる方が死ぬ日を選べるわけがありません。
ですから、定休日なんて作れないんです。
そこでこの六曜という迷信は「使える!」となったという説です。
なぜこの迷信が作為的なものだと考えられるか?にも理由があります。
それは、もともとの漢字と現在の漢字が違っていること。
「仏滅」は昔は「物滅」と書きました。
モノをなくしやすい日なので気をつけましょうね、という日だったんです。
ぜんぜんイメージ違いますよね。
さらに「友引」は「共引」でした。
これは共に引き分ける日、『勝負のつかない日』、という意味でした。
それを「仏が滅する」「友を引き連れていく」といった強いイメージにしていることから、
恐怖の感情を利用した洗脳の手法とも考えられます。
このように漢字を変更したのが誰なのかもわかりませんが、
ここまでしておいて
「葬儀に携わる方々のお休みのため」とはちょっと考えにくいんですよね〜。
と、これ以上こねくりまわしても答えは出ないので、そろそろまとめにかかりましょう ^^;
さいごに
いまだ多くの人が頑なに信じる大安・仏滅・友引等の「六曜」について、
思いっきり「迷信」であったことがわかっていただけましたでしょうか。
わたしも縁起をかつぐのが大好きな日本人です。
やはり自分の結婚式には仏滅は避けましたし、
はじめに書いたとおり父親の葬儀についてはかなり悩みました(汗)
ここまで広まり、信じている人が多いと、
「出どころも根拠も不明だし仏教や神道とも関係ないんだ」
と言ったところで親族の目もありますし、悩ましいところですよね。
ですが、葬儀に関してはいつ亡くなるかなどわかるはずもありません。
お寺や葬儀業者、親族の都合などで理想の日取りができないこともあります。
なのでもしお葬式やお通夜が仏滅を避けられないような場合、
もし気にされる方がいらっしゃるようなら、
安心してもらえるようにお坊さんから言ってほしいと伝えておくといいと思います。
こういったパターンも多いはずですから、きっと上手く安心させていただけると思いますよ^^
-
お葬式・お墓参りのしきたり・マナーまとめ
お葬式やお墓参り、とくに葬儀でのしきたりやマナーで戸惑うことも多いんじゃないでしょうか。しかも宗派によって違うことなども混乱しますね。供養・慰霊についての不思議や疑問、豆知識をまとめてみました。